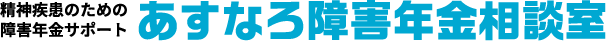2020年02月05日
障害年金には障害(病状)の程度によっていくつかの等級に分かれています。ここではこの障害年金の等級についてご紹介いたします。
障害年金の等級
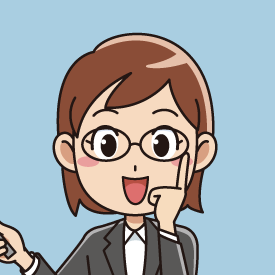
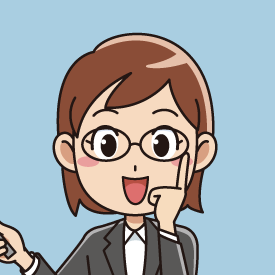

各等級の内容
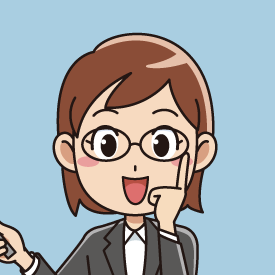

障害の等級を認定する場合の基準となるものは省令で障害の状態の基本が1級から3級と障害手当金まで下記のように決められています。
1級・・・身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用便ずることを不能ならしめる程度のものとする。
この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
たとえば身の回りのことはかろうじてできるがそれ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち病院内の生活で言えば活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるものであり家庭内の生活で言えば活動の範囲が概ね就床室内に限られるものである。
2級・・・身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは必ずしも他人の助けを借りる必要はないが日常生活は極めて困難で労働による収入を得ることができない程度のものである。
例えば家庭内のきわめて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるがそれ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないものすなわち病院内の生活で言えば活動の範囲が概ね病棟内に限られるものであり家庭内の生活で言えば活動の範囲が概ね家屋内に限られるものである。
3級・・・労働に著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また傷病が「治らないもの」にあっては労働が制限を受けるかまた労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(傷病が「治らないもの」については障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても三級に該当する)。
障害手当金・・・「傷病が治ったもの」であって労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
※障害手当金は初診日から五年以内に傷病が治り障害手当金の状態に該当しているときに支給されます。
障害治ったから五年以内に行わなければなりません。障害が治ったとは症状が固定し治療を行ってもその効果が出る見込みがないものを言います。精神の障害の場合には傷病が治ったものと認められる場合はあまりありません。
肢体の障害などで(脳梗塞など)傷病が治ったと認められる場合があります。

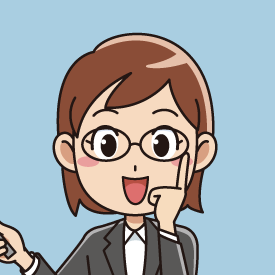

精神の障害の等級
各障害の等級
知的障害
1級・・・知的障害があり食事や身の回りのことを行うのに全面的な援助が必要であってかつ会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため日常生活が困難で常時援助を必要とするもの。
2級・・・知的障害があり食事や身の回りのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であってかつ会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため日常生活にあたって援助が必要なもの。
3級・・・知的障害があり労働が著しい制限を受けるもの。
発達障害
1級・・・発達障害があり社会性やあコミュニケーション能力が欠如しておりかつ著しく不適当な行動が見られるため日常生活への適用が困難で常時援助を必要とするもの。
2級・・・発達障害があり社会性やコミュニケーション能力が乏しくかつふてきような行動が見られるため日常生活への適用に当たって援助が必要なもの。
3級・・・発達障害があり社会性やコミュニケーション能力が不十分でかつ社会行動に問題が見られるため労働が著しい制限を受けるもの。
てんかん
1級・・・十分な治療に関わらずてんかん性発作のAまたはBが月に1回以上ありかつ常時介護が必要なもの。
2級・・・十分な治療に関わらずてんかん性発作のAまたはBが年に2回以上もしくはCまたはDが月に1回以上ありかつ日常生活が著しい制限を受けるもの。
3級・・・十分な治療にかかわらずてんかん性発作のAまたはBが年に2回未満もしくはCまたはDが月に1回未満ありかつ労働が制限を受けるもの。
【発作のタイプ】
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず転倒する発作
C:意識を失い行為が途絶するが倒れない発作
D:意識障害はないが随意運動が失われる発作
統合失調症
1級・・・統合失調症によるものにあっては高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他、妄想・幻覚等の異常体験が著明なため常時の介護を必要なもの
2級・・・統合失調症によるものにあっては残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害その他妄想・幻覚等の異常体験があるため日常生活が著しい制限を受けるもの
3級・・・統合失調症によるものにあっては残遺状態または病状があり人格変化の程度が著しくないが思考障害その他、妄想・幻覚等の異常体験があり労働が制限を受けるもの
双極性障害
1級・・・双極性障害によるものにあっては高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期がありかつこれが持続したり頻繁に繰り返したりするため常時の介護が必要なもの
2級・・・双極性障害によるものにあっては気分、意欲・行動の障害および思考障害の病巣期がありかつこれが持続したりまた頻繁に繰り返したりするため日常生活が著しい制限を受けるもの
3級・・・双極性障害によるものにあっては気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期がありその病状は著しくないがこれが持続したりまた繰り返し労働が制限を受けるもの
肢体の障害の等級
上肢の障害
上肢の障害においてはつまむ、握る、タオルを絞る、紐を結ぶ、匙で食事、顔を洗う用便の処置をする、ズボン着脱、靴下を履くなどの動作において著しく支障が生じている場合または動作が出来ない場合は1級、著しく支障が生じている場合は2級その他支障が生じている場合は3級認定される可能性があります。
下肢の障害
片足で立つ、座る、、深くお辞儀をする、歩く、、立ち上がる、階段を上る、階段を降りるなどの行為において著しく支障が生じているかまたはできない場合1級、著しく支障が生じている場合は2級、支障が生じている場合は3級に該当する可能性があります。
また補助用具の使用でも常時杖や松葉杖、車椅子などの補助用具を使用している場合などはそれぞれ1級~3級のどの等級に該当するかにおいて審査の対象となります。
※上肢のみ下肢のみの障害に比し上肢下肢ともに障害がある場合の方がより上級の等級に該当する可能性が高いといえます。
カテゴリ:障害年金の基礎知識