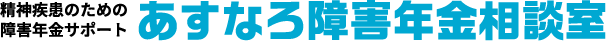2019年11月28日
障害年金の手続きにおいて初診日の特定はとても重要な部分です。一方で少しわかりづらい点もありますのでここで詳しくご説明いたします。
初診日とは
障害年金の初診日とは当該傷病(障害)で初めて医師(歯科医師)の診断を受けた日を言います。
診断を受けた日とは病名が決まった日ではなく症状が出て初めて病院を受診した日のことを言います。
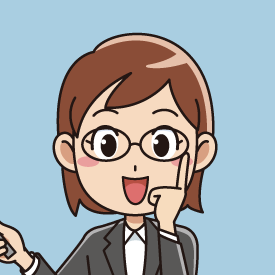

初診日の重要性
初診日が特定されるとその日を基準に色々な点が判断の起点となりますのでとても重要になってきます。
保険料の納付要件
初めに特定された初診日を基準に保険料の納付要件が決定されます。保険料の納付は初診日以前の納付状況で判断されます。
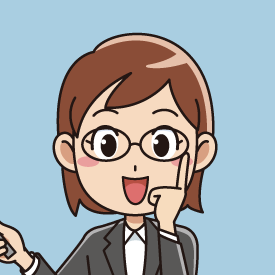

厚生年金と国民年金の違い
初診日を基準に初診日に会社員などで厚生年金に加入していた場合は現在退職していたとしても障害厚生年金の支給対象となります。
一方初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金(国民年金)の対象となり初診日を基準に障害厚生年金と障害基礎年金の振り分けが行われます。
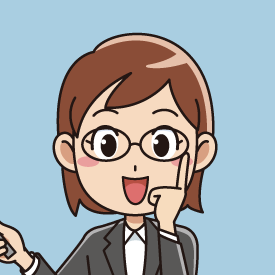
初診日の例外
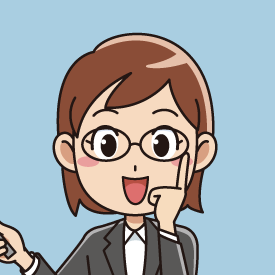

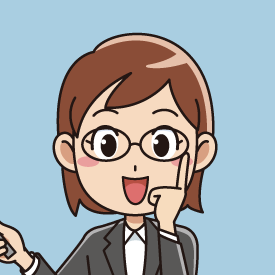

初診日の証明に必要な書類
各種書類
初診日に必要な書類には受診状況等証明書、受診状況等証明書が添付できない申立書、初診日に関する第三者からの申立書等があります。
カルテに基づいて作成された受診状況等証明書が初診日の証明としては最も確実でポピュラーなものですがそれ以外でも初診日を証明できる書面であれば書面の種類は問いません。

初診日の受診は書面で証明する必要があります。
受診状況等証明書
前述しましたが受信状況等証明書は障害年金の初診日の特定において最も重要でポピュラーな証明書です。年金事務所の窓口に障害年金の手続きを行いに行った場合にも一番最初に渡される書類がこの受診状況等証明書です。
受診状況等証明書には①~⑩までの記載欄があります。
①氏名・・・特に問題はありませんが、結婚等で姓が変わる前に病院を受診していた場合には現在の氏名と異なる氏名で証明書が作成される場合がありますので注意が必要です。
②傷病名・・・傷病名の欄も受診状況等証明書の内容の中で重要です。一方で傷病名はカルテに記載されていた証明がそのまま受診状況等証明書にも記載されますので証明書作成を行った時点で先生や病院に変更お願いすることはできません。
③発病年月日・・・病院が認識している発病の年月日が記載されます。発病年月日は初診日を特定する上で参考となる年月日で初心を特定する上でも重要な記載欄となります。
④傷病の原因または誘因・・・他に当該ご病気の原因または誘引となったご病気がある場合はここに記載されます。
⑤発病から初診までの経過・・・発病から初診までの経過がこの欄に記載されます。受診状況等証明書作成病院以前に受診している病院がある場合はこの欄に前医あり等の記載が行われます。障害年金の請求を行う上でとても多いケースが受信状況等証明書の作成依頼を行った場合に当該記載欄に前医ありと記載されていて初診日の特定が行えなくなってしまうケースです。
※前医の紹介状がある場合は紹介状有りに〇をつけてもらい紹介状のコピーを添付してもらいます。
⑥~⑩欄・・・カルテの内容に基づいて記載されます。
受診状況等証明書が添付できない申立書
受診状況等証明書が添付できない場合にはこの受診状況等証明書が添付できない申立書を添付します。
年金事務所の窓口では時として受診状況等証明書が添付できなくてもこの受診状況等証明書が添付できない申立書を添付すれば障害年金の手続きが進み年金が受給できるような説明を受けることがありますがそのようなことはありません。
初診日は例外を除いて必ず何らかの証明書によって特定する必要がありますのでこの受診状況等証明書が添付できない申立書を添付した場合はそれ相応の他の証明書類を付ける必要があります。
他の証明書の例:障害者手帳申請時の診断書の写し、健康診断の記録、母子健康手帳、健康保険の給付記録、お薬手帳、糖尿病手帳、、領収書、診察券、小学校や中学校等の健康診断の記録や成績通知表、第三者証明等)。
初診日の関する第三者からの申立書(第三者証明)
初診日に関する第三者からの申立書は初診日を特定することができる証明書が他にない場合に初診日前後のご病気についての状況をご存知の第三者2人に証明書を作成していただくことで初診日を特定する申立書です。
第三者とは三親等内の親族以外の方をいいますので両親や兄弟などのご家族、叔父叔母、祖父母は含まれません。両親のご友人や学校の先生、ご自身のご友人などが対象となります。
20歳前傷病による障害基礎年金の場合は基本的に当該初診日に関する第三者からの申立書を提出することで初診日が特定されます。
一方で初診日が20歳にあるそれ以外の傷病の場合には当該初診日に関する第三者からの申立書を提出する以外に何らかの補足資料を提出する必要があります。
上記のような異なる扱いがなされる理由の一つとして20歳以前は基本的に障害基礎年金の対象となりますが20歳以後は厚生年金加入期間が含まれる場合があり厳密に初診日を特定する必要があるからです。
カテゴリ:障害年金の基礎知識